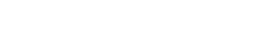【No.6】河川敷地内における防草対策や自然生えした樹木管理の効率化
- 環境・緑・水

募集期間
2022年08月30日~2026年08月31日
担当課
緑政土木局・河川工務課
本課題のポイント
解決したい課題
河川敷地内の自然生えした樹木や雑草による通行支障、景観悪化、洪水リスク増大の防止と効率的な管理手法の構築。特に急勾配の河川法面での人力作業の困難さや、植樹区間でのリフト車等の機械利用制限、コンクリート目地から生える樹木の根絶困難および護岸損傷問題を含む。
想定する解決策
費用対効果の高い防草対策の提案。特に、手入れが極力不要な状態を維持する方法や除草剤使用に代わる管理手法や機械・人力作業が難しい箇所にも適用可能な手法。
提案者側の想定メリット
・事業における社会的意義の創出
・提案された技術、工法等の効果検証
・新たなサービス展開やビジネスモデル構築の機会
・本市との連携による知名度・企業イメージの向上
・幅広い市民層へのアプローチを通じた新たな市場開拓や顧客基盤の拡大
公民連携に期待する事項
・樹木や草類の生育状況や条件に関する知識や知見
・技術やノウハウの共有による持続可能な防草対策の支援
本課題の詳細
実現したい未来
河川敷が快適で安全に利用でき、景観が保たれ、洪水リスクが低減された状態。手間とコストを抑えた維持管理が実現している。
課題の背景
河川法面の未舗装部分は、雑草や樹木が繁茂し、通行障害や景観悪化を招いている。また、舗装部分は、コンクリート目地から生える樹木の根絶困難による護岸損傷や空洞化が発生。また、樹木繁茂は河積阻害を引き起こし、洪水の要因の一つとなっているとも言われている。特に集中豪雨が頻発する昨今では、樹木の繁茂が洪水の一因とされる。河川法面が急勾配であること、近接して植樹がされている区間ではリフト車等での機械作業の制約がある一方、周辺環境への配慮から除草剤等薬剤の使用が原則禁止となっている(「名古屋市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正使用に係る基本方針」)。
課題の現状
除草作業は、業務委託で年2回程度、樹木の伐採は適宜必要に応じて実施している。除草作業や樹木伐採は一度手を入れたら完了ではなく、 毎年継続的に実施していくことが不可欠である一方、労務単価等の上昇により年々維持管理費も高くなり、予算の確保も難しくなっている。市民からの陳情も多数寄せられており、必要に応じて各土木事務所で除草作業等を行うなど、市職員の負担も増加している。
例えば、名古屋市で管理している山崎川では、以下の写真のように、雑草や樹木が繁茂するため、定期的に除草作業や樹木伐採を実施している。
<山崎川の萩山橋周辺 施工前>
_無害化済-1024x683.jpg)
<山崎川の萩山橋周辺 施工後>
_無害化済-1024x576.jpg)
また河川法面での作業は、平坦な場所での作業に比べ、転倒や機械による怪我のリスクも高いことが課題となっている。
提案してほしいこと
維持管理コストを抑えつつ、効率的に防草・樹木管理ができる手法。特に、手入れの必要が少なく、除草作業に代わる効果的な技術や管理方法。
例)防草シート、マット、除草剤に代わる樹木の発達を阻害する施策
提案者のメリット
・実証実験により、リアルな運用データや利用者の声を得ることができ、自社サービスや技術のブラッシュアップに繋げられる。
・将来的に本市以外の他都市へサービスを展開できる可能性がある。
・公民連携による社会課題解決の実績を積むことができ、企業イメージやブランド価値の向上が期待できる。
募集概要
| 担当課 | 緑政土木局・河川工務課 |
|---|---|
| 担当部署の事業の概要 | ・河川、水路等(都市農業課の主管に属するものを除く。)の新設及び改良の工事並びに維持修繕に関すること。 ・ポンプ施設からの排水の管理に関すること。 ・河川の浄化及び環境整備(河川部所管施設に係る緑道の整備を含む。)に係る事業の実施に関すること。 ・水防計画並びに水防施設等の設置及び管理に関すること。 |
| 検討経緯・これまでに実施したことがある施策等 | 【樹木伐採】 ・人力や機械による地際での伐採 ・表皮の皮剥ぎによる衰退化 ・伐採後の断面に傷を付けることによる衰退化 →短期間で再繁茂するなど、効果はあまりない。 【除草】 ・砕石舗装や防草シートで覆う。 →整備コストがかかるため、市域全体での施工が困難。 ・民地に面している箇所において、場所を限定して除草回数を増やす。 →維持管理コストは年々縮減傾向にあり、他の事業の予算を削るなどの対応をしており、影響が大きい。 |
| 提供企業に求める専門性 | ・樹木や草類などの生態に関する知識や知見 ・防草効果、樹木生育阻害効果に有効な技術 |
| 提案できるリソース等 | ・「どりょくん日記」等への掲載 ・試験施工箇所の提供 |
| 実施予定時期 | 随時 ・実現可能性の高い提案については、本市と打ち合わせを行い、実施予定期間等について協議します。 |
| 提案の選定方法 | 提案内容が妥当であれば採用数を絞込みません。 |
| 予算措置の可能性 | 提案事業の試験施工等の結果により、来年度以降の予算措置の可能性があります。 |
| 備考/その他参考情報 |
——— |