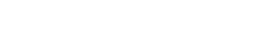【No.49】ラムサール条約湿地都市認証や藤前干潟の認知度向上
- 教育
- 環境・緑・水
- ブランド向上

募集期間
2025年09月26日~2027年03月31日
担当課
環境局環境企画部環境企画課
本課題のポイント
解決したい課題
ラムサール条約湿地都市認証および藤前干潟の認知度向上。
市民にとってイメージしづらい国際認証の意義を効果的に伝え、都市ブランドと環境意識の向上を図る。
想定する解決策
・市民への広報・啓発活動
・企業とのコラボによるイベントや商品展開
・名古屋市内の小学校向けの教育教材の提供(小学校のタブレットに掲載)
・エコパルなごやでの出張授業
・SNSや動画などデジタルメディアを活用したプロモーション
提案者側の想定メリット
・国際的な都市ブランドとの連携による企業イメージの向上
・環境分野でのSDGs・CSR活動の実績として活用可能
・市民との接点によるブランド認知の拡大
・環境ビジネス分野での市場展開と認知度向上
公民連携に期待する事項
・市と企業が協力して持続可能な啓発活動を展開
・市民参加型のイベントやキャンペーンの共同企画
・教育・広報・商品開発など多角的な連携の実現
本課題の詳細
課題の背景・現状
名古屋市は2025年にラムサール条約湿地都市として認証されましたが、市民アンケートによると藤前干潟の訪問経験者は約30%にとどまり、認証の意義や干潟の魅力が十分に伝わっていない現状があります。過去の「ごみ非常事態宣言」などの環境施策とのつながりを活かし、認知度向上と市民参加を促す取り組みが求められています。
(注)「ラムサール条約湿地都市」について
ラムサール条約は、湿地の保全と持続可能な利用を目的とした国際条約です。「湿地都市」は、湿地の保全や再生、環境教育、市民参加などに積極的に取り組む自治体に与えられる称号で、名古屋市は2025年に認証されました。
 写真左)ムソンダ・ムンバ ラムサール条約事務局長
写真左)ムソンダ・ムンバ ラムサール条約事務局長
写真右)環境局嶋担当局長(環境都市推進)
(注)「ごみ非常事態宣言」について
名古屋市は増加するごみを処理するため、藤前干潟に埋立処分場を建設する計画を立てました。しかし、渡り鳥にとって重要な休憩場所であったことから、保全を求める市民の声が高まりました。「市民生活」と「渡り鳥」どちらが大切か議論を重ねた結果、どちらも大切であるという結論を出し、1999年に名古屋市は埋立計画を中止し、「ごみ非常事態宣言」を発表しました。そして、市民・事業者の方々と徹底的にごみを減らす取り組みを進め、2年間で20%の削減を達成し、2002年に藤前干潟はラムサール条約湿地に登録されました。その後、「分別文化」は確実に根付き、2003年には自治体環境グランプリにおいて市民と名古屋市が連名で「環境大臣賞」と「グランプリ」を同時受賞し、全国的にも評価されました。(詳細はこちら)
実現したい未来
名古屋市が環境先進都市として国内外に認知され、市民が藤前干潟や湿地の価値を理解し、保全活動に積極的に参加する未来を目指します。特に若年層や子育て世代が自然と触れ合う機会を増やし、持続可能な環境意識を育むことで、SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」および目標15「陸の豊かさも守ろう」等の達成にも貢献します。藤前干潟を中心とした地域の自然環境が、市民の学びと行動の場となり、都市ブランドと環境価値の両立を実現します。
提案して欲しいこと
・市と連携して実施可能な企画(イベント、教材、商品など)
(例)「藤前干潟ふれあい事業」における主催事業の共催 (参考:R7年度 藤前干潟ふれあい事業チラシ)
・企業とタイアップした広報キャンペーン
提案者側のメリット
・国際的な都市ブランドとの連携による企業イメージの向上
・環境分野でのSDGs・CSR活動の実績として活用可能
・市民との接点によるブランド認知の拡大
・環境ビジネス分野での市場展開と認知度向上
募集概要
| 担当課 | 環境局環境企画部環境企画課 |
|---|---|
| 担当部署の事業の概要 | ・環境保全に係る教育及び学習に係る企画及び調整 ・藤前干潟を活用した環境学習の推進 ・環境学習センターの運営 ・なごや環境大学の推進 |
| 検討経緯・これまでに実施したことがある施策等 | ・野鳥観察、干潟体験、写真展、スタンプラリーなどの環境教育プログラム ・藤前干潟学習のためのウェブサイト開設 ・啓発リーフレットの作成(日本語版・英語版) ・プロモーション動画の作成(日本語版・英語版) |
| 提供企業に求める専門性 | 特になし |
| 提案できるリソース等 | ・名古屋市環境学習センター(エコパルなごや)展示室の利用 ・環境省が所管する藤前干潟関連施設との連携 |
| 実施予定時期 | 提案内容に応じて順次実施 |
| 提案の選定方法 | 提案内容が妥当であれば採用数を絞らない |
| 予算措置の可能性 | 次年度以降に予算措置の可能性がある |
| 備考/その他参考情報 |
・実施には当課以外にも藤前干潟協議会、環境省、NPO法人藤前干潟を守る会との調整が必要となる ・市公式HP「藤前干潟の保全・活用」について:リンク ・市公式HP「藤前干潟やイベント情報」について:リンク |